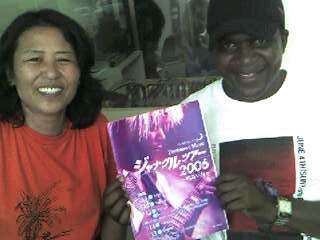いろいろな所で、多くの人たちの心感じる熱い声援、本当に
いろいろな所で、多くの人たちの心感じる熱い声援、本当にありがとうございました。議員活動中の様々な再会出会いは彼女の次の活動にとって大きな財産になることと思います。これからもどうぞ宜しくお願いします。
昨夜は二人で開票速報を見ながら、結局朝6時にマスコミ取材があるまで徹夜でいろいろな話しをしました。
この間の6年で何も予定の入っていない日はどれだけあったのだろう、月に2日あれば…というくらいスッピンでいられる日はなかったと思います。
自分で飛び込んだ世界ですから、よっぽどでないかぎり弱音をはかず、話がややこしくなるほど頭の働きがシャープになり、前へコトを進める手だてを行く通りも絞り出していました。
もともとトロント大学で<発生生物学>を専攻していたので物事の発生や成り立ち、構造と変化…温度や湿度や触媒や…
によって不確定な環境/状況が変化していく在り用への視点と対応は思考回路に焼き付けられているのだと思います。
そして神戸芸工大の大学院で「教育のデザイン」を研究し博士号をとっているので、人とシステムをデザインするのは専門家です。
 どちらも正しい情報を的確にインプットしないと正確な回答は得られないし、ソフトをきちんと把握してないとハードへは至らないことを充分承知している人です。
どちらも正しい情報を的確にインプットしないと正確な回答は得られないし、ソフトをきちんと把握してないとハードへは至らないことを充分承知している人です。そんな研究者で教育者である彼女がたまたま「政治家」であった6年間といえます。
「この問題を解くにはソフト/ハードどんな必要十分条件が必要か?」流動的に変化する状況の中で、それに対応する条件をクリアしながらの政治家運動をしていたのだと思っています。
僕にはどんな政治家でも、やはりひとつのことを掘り下げてきたプロフェショナルな専門家的深みが必要だと感じています。視点や思い、発想のアマチュアリズムと、形にしていくプロな技の両方が求められるのだと思います。
余談ですが山本太郎さんの想いの熱さは政界という場でからまわりし、足下をすくわれ「孤立化」していきそうな気がしてしょうがないです。クールでしたたかな仲間が支えないと、いとも簡単に潰されかねない…と感じます。
さて、話はタニオカに戻しますが、昨夜の開票速報を見ていて谷岡の同志、山形の舟山やすこさんが接戦で破れた時、僕が思ったことは最後に谷岡だけが当選したらどうしょうか?ということでした。
どんな闘いでも問題を共有分担できる仲間がいて、支えあい共感できるパートナーがいなければ孤立し(分断し孤立化させるのが常の敵の手ですから…)、最後は燃え尽きるか萎えしぼんでフェイドアウトするしかないでしょう。
多くの国民の付託という重みはひとりで背負うには重すぎるし、頭がいくつもあって、手が何本もなければ多くの問題と課題解決という国会現場での多岐にわたる戦線には対応出来ないのですから…。
そんな不安を感じ亀井あきこさんも負け…という状況、それはタニオカがこの人とだったらと声をかけた実力も意志も強いよりすぐりの女性議員の仲間、この仲間とだったらやり切れるという替えがたい同志、その仲間がいない中でこれからがどんな闘いになるのかを想像し、その重さでタニオカは壊れるかもしれないと思いました。
その時、実はタニオカも同時にそれを思っていたことが後でわかりました。
その意味で彼女が比例で落選した時は「安堵」というのが本音です、それは彼女も同様であったと思います。
政治家を辞めるということは活動を止めることでは全くありません、むしろ議員という枠では出来なかったことをタニオカ自身の社会化として出来る新しい運動の始まりと考えて下さい。
 おそらく落選の報を聞いた瞬間からすでにタニオカは次のことへ頭を切り替えていたと思います、その時からアイデアは彼女の頭の中を走り始めています。
おそらく落選の報を聞いた瞬間からすでにタニオカは次のことへ頭を切り替えていたと思います、その時からアイデアは彼女の頭の中を走り始めています。福島の人たちのこと忘れる訳ありません。原発の廃炉から後始末のこと忘れる訳ありません。この国の未来のこと頭から離れる訳ありません。
議員時代には出来なかったことを、彼女「らしく」始めると思います…いずれきっと彼女は皆さんに声を掛けることと思います。その時まで皆さんもご精進を…この間、本当にありがとうございました。
旦那は再び腰を落ち着け、山の入ります…ゲリラは「山」に籠ると決まってますので…最近中山間地に入って来る若い衆がたくさんいますが、今回街でビラ配りやって「街」の人たちのあきらめて<自棄>しているような目と較べ、本当にきれいな目をしていると感じます。
 自棄から<自暴>へ向かいつつある状況を感じつつ、山から回復の「みどりの風」を送りたいと思います。
自棄から<自暴>へ向かいつつある状況を感じつつ、山から回復の「みどりの風」を送りたいと思います。*タニオカが20日
大須観音で最後の街宣をしたスピーチを一度ニコニコ動画で見て下さい。
タニオカのHPで見られますので…。